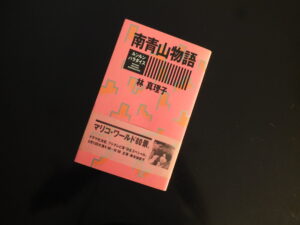岡本太郎が43年間実際に暮らした住居兼アトリエがそのままに
表参道駅から骨董通りを高樹町方面に10分ほど歩き、左側に一本入った路地裏に忽然と出現する南国情緒漂う植物が生い茂る不思議な空間が目に飛び込んでくる。これが岡本太郎が実際に40年以上暮らし、多くの傑作を世に送る出したアトリエ兼自宅を改装した、岡本太郎記念館である。本館建物やその中にあるアトリエは、当時のまま残されており、太郎ファンにとっては奇跡の場所である。
岡本太郎記念館は、岡本太郎(1911 ~1996)が、1953 年から84歳で没する1996年までの43年間、自宅兼アトリエとして実際に暮らし制作に励んだ建物を、没後記念館して改装し一般公開したものである。作品鑑賞だけでなく、アトリエの制作風景や庭に面した客間などあらゆる角度から岡本太郎の世界観に触れることができる稀有な場所だ。また、様々な企画展などを通じて、岡本芸術の多様性と力強さを感じることができる貴重な空間として人気を博している。

岡本太郎記念館には、多くの彫刻、デッサン、エスキースなどが展示保存されている。1階奥のアトリエには、岡本太郎が実際に使用した筆や絵具、棚に積まれた未完成のキャンバスなどが当時のまま無造作に置かれており、アトリエの奥から岡本太郎がふらっと出てきそうなリアルな空気感が今でも漂っている。アトリエの奥に向かって右手には岡本自身が弾いたアップライトピアノがある。お気に入りはショパンの軍隊ポロネーズ。かつてTVで本人が弾いている姿を見たことがある。お世辞にもうまいとは言えないが、強烈で個性的な演奏は、今でも耳に焼き付いている。2階には油絵、彫刻などが展示されている。館内では写真撮影も自由である。


正面にある建物は、岡本太郎のパリ留学時代の友人で、ル・コルビュジェの弟子としてモダニズム建築を実践した建築家・坂倉準三が設計した。岡本太郎の希望により、積み上げたブロックの外壁の上に乗った屋根は、側面が凸レンズの形をしたユニークなデザインとなっている。1954年、岡本太郎はここに住居兼アトリエを構え、「現代芸術研究所」と名づけて創作活動の拠点にした。以来、岡本太郎は、この場所から唯一無二の“岡本芸術”を世の中に送り出してきた。大阪万博(1970年)の太陽の塔の構想を練ったのもこの場所である。
1996年に岡本太郎が亡くなると、生涯のパートナーだった岡本敏子の「岡本太郎を次の時代に伝えたい」という熱い思いから、没後わずか2年でこの場所に「岡本太郎記念館」を開設し、岡本敏子(2005年に急逝)は館長に就任した。坂倉準三が設計した旧館は修復にとどめ、隣接する2階建ての彫刻のアトリエだった建物を展示棟に建て替え、財団法人運営の公的なミュージアムとして再出発した。

岡本太郎記念館の運営を担う財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団は、岡本太郎が亡くなった翌年の1997年の2月に設立された。現在財団法人の常務理事は岡本敏子の甥の平野暁臣氏で、顧問として裏千家前家元・千玄室氏、実業家・糸井重里氏らが名を連ねている。


帽子を深々とかぶりとぼとぼと歩く姿をよく見かけたものだ。
全国各地に、岡本太郎の作品が街の一部として存在している。有名な作品では、こどもの城の『こどもの樹』・川崎市岡本太郎美術館の『母の塔』・数寄屋橋公園の『若い時計台』、渋谷駅の壁面をかざる巨大な絵画作品などがある。